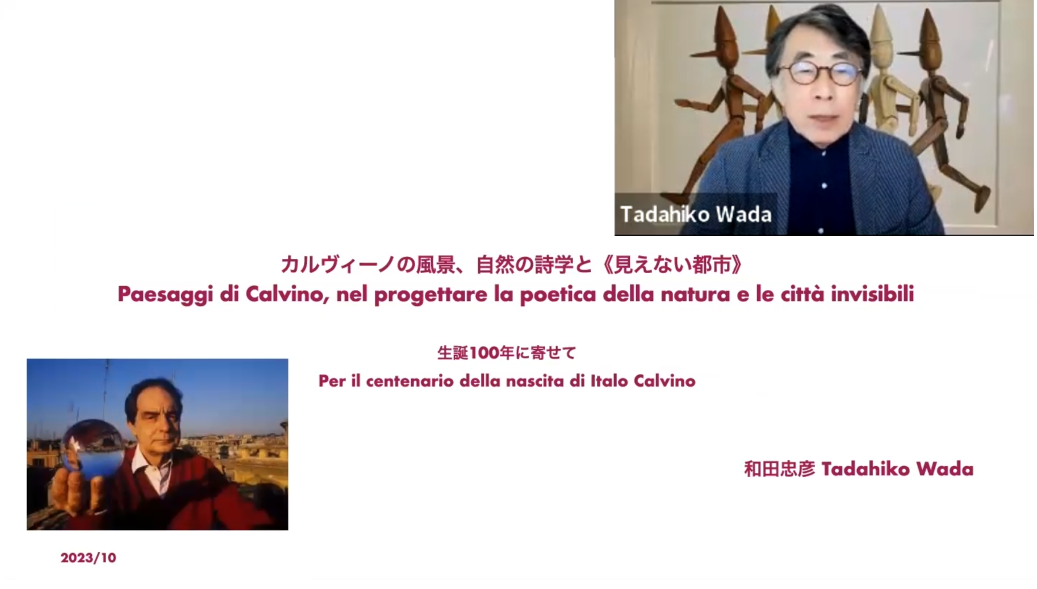生誕百年を機に、詩学を構想する企てのなかでカルヴィーノがどんなふうに風景を描いてきたのか、そしてその中間地点としてカルヴィーノがたどり着いた『見えない都市』という作品がカルヴィーノ全体の歩みのなかでどんな意味を持っているのかについて考えてみる。
まず作家の歩み全体を振り返ってみる。そののち物語のなかでカルヴィーノがどんなふうに世界を描いてきたのか、言い換えれば世界をどんなふうにみつめ眺めてきたのかを、初期の作品を手がかりに確認する。まず最初にカルヴィーノが実際に暮らした街、いわば«伝記的»な都市を、«見えない都市»との対比で«見える都市»として読んでみる。そこからカルヴィーノが『見えない都市』という作品に象徴される«見えない»ものを言語化する方法と詩学にたどり着き、格闘を続けた軌跡をたどり直してみる。その後、『見えない都市』について、都市の相貌のなかにつねに見え隠れする街、『見えない都市』の旅人マルコ・ポーロの故郷ヴェネツィアがどんな風に関わっているのか、そしてさらにそうして町のありようを描くことでカルヴィーノが都市あるいは人が暮らす空間についてどう考えるようになっていったのかを見ていく。その結果として、カルヴィーノがたどり着いたひとつの詩学もしくは美学を、仮に«自然の詩学»と呼ぶことにする。それがどんなものなのか、そしてその結果としてカルヴィーノが最終的65歳になる直前にこの世を去るまで探求し続けたその物語のありようが実は哲学的なと言ってもいいかもしれない«省察»と呼べるような思考の様態がもたらす散文詩のような世界ではなかったのかということを確かめてみる。
動画のご視聴はこちら
和田 忠彦
1952年、長野市生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。東京外国語大学名誉教授。1999年より東京外国語大学教授、大学院研究科長、副学長等を経て、2017年3月退任。
イタロ・カルヴィーノ、ウンベルト・エーコ、アントニオ・タブッキをはじめとするイタリア近現代文学の翻訳で知られる。イタリア文化普及に貢献したとして、2004年度イタリア共和国「連帯の星」コンメンダトーレ叙勲、2011-2012年度イタリア国家翻訳大賞受賞。
著書に『ヴェネツィア 水の夢』、『声、意味ではなく』、『ファシズム、そして』、『タブッキをめぐる九つの断章』『遠まわりして聴く』など多数。近年の訳書にアントニオ・タブッキ『とるにたらないちいさないきちがい』(2017)、『イザベルに』(2018)、イタロ・カルヴィーノ『魔法の庭・空を見上げる部族 他十四篇』(2018)、ウンベルト・エーコ『永遠のファシズム』『女王ロアーナ、神秘の炎』(2018)、『ウンベルト・エーコの文体練習(完全版)』(2019)、『文学について』(2020)、『中世の美学』(2022)など。